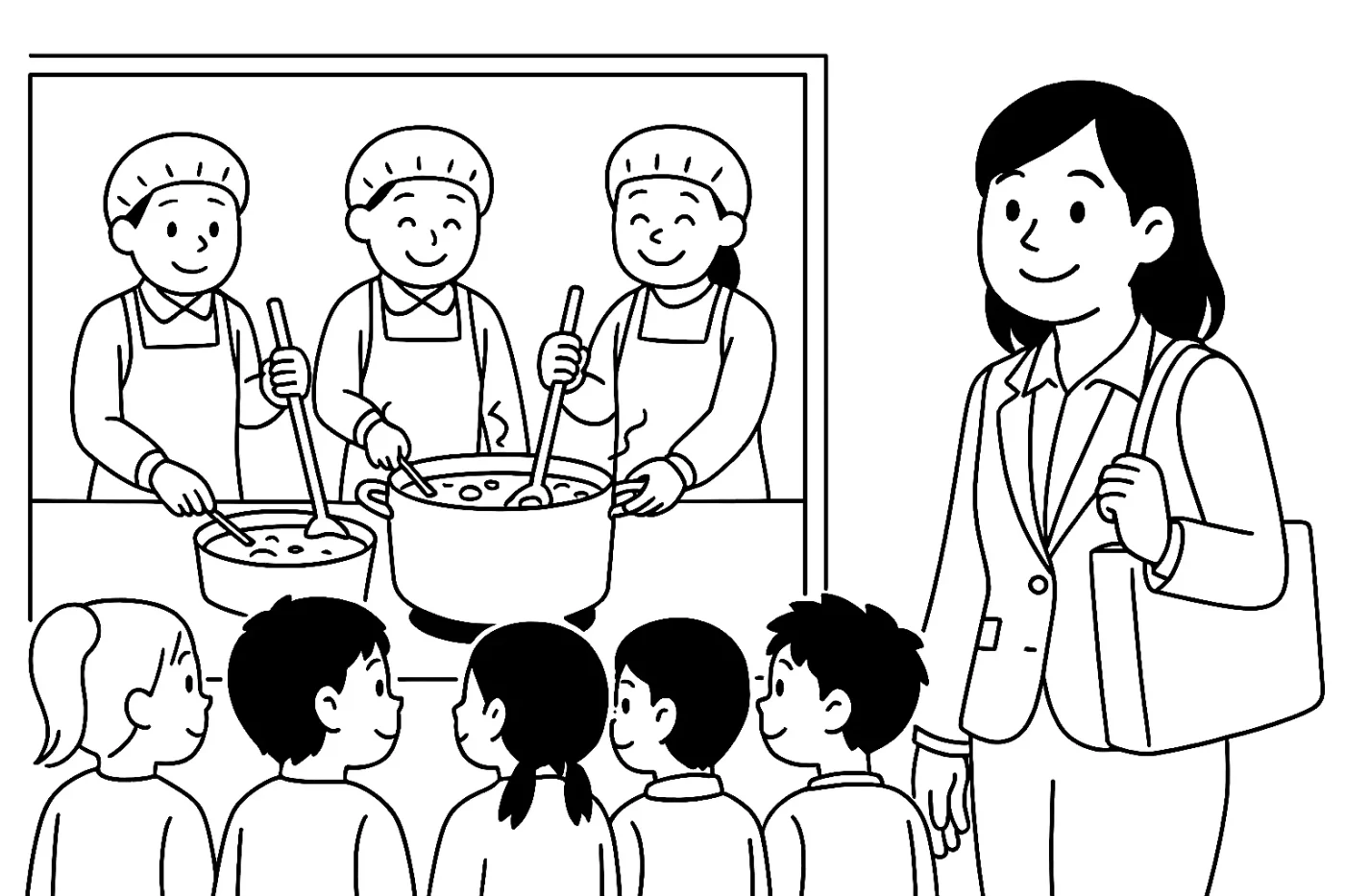※この物語はフィクションです。
前回までのあらすじ: 発芽カリキュラムの実践が始まったものの、給食をテーマにした教科横断の授業で美咲は壁にぶつかった。子どもたちは困惑し、国語の作文も算数の栄養計算もうまくいかない。美咲は子どもたちと一緒に学ぶ姿勢を見せ、徐々に信頼関係を築き始めていた。
今回の見どころ: 給食センター見学で大きな転機が訪れる。三千食を作る現場の迫力と栄養士の熱い思いに触れた子どもたち。見学後、教室に戻った彼らの目には今まで見たことのない輝きがあった。発芽カリキュラムの真の可能性を感じ始めた美咲だが、この後に予想外の試練が待ち受けているとは、まだ知る由もなかった…
二週間後、美咲と子どもたちは給食センターを見学していた。
巨大な調理場で、白衣を着たスタッフが大きな釜でカレーを作っている。
「一日に三千食作るんですよ」
案内してくれた栄養士の田辺さんが説明した。
「三千食?」
子どもたちが驚いた。
「この学校だけじゃなくて、近隣の五つの学校の給食を作っています」
健太が手を挙げた。
「メニューはどうやって決めるんですか?」
「栄養バランスを考えて、一週間、一ヶ月単位で計画します。子どもたちの成長に必要な栄養素を計算して、それに合わせて食材を選んでいます」
花音が質問した。
「一番大変なことは何ですか?」
「食物アレルギーの子どもたちへの対応ですね。一人ひとりに合わせて、別のメニューを用意することもあります」
子どもたちは真剣に聞いていた。
「給食を残さず食べてもらえると、とても嬉しいです」
田辺さんの言葉に、子どもたちは深くうなずいた。
見学から帰った後、教室は興奮状態だった。
「すごかった!」
「三千食なんて想像できない」
「今度から絶対に残さない」
美咲は子どもたちの反応を見て、発芽カリキュラムの可能性を感じていた。
国語の時間、子どもたちは見学で学んだことを作文にまとめた。
健太は「三千人の笑顔のために」というタイトルで、給食センターで働く人たちの思いを書いた。
花音は「食べることの意味」というタイトルで、食物アレルギーの友達のことを思いながら給食について考えを深めた。
算数の時間は、三千食分の材料を計算した。
「ニンジンが三百キロ必要なんだって」
「一日でお米が百五十キロ」
「僕たちが食べる分は、全体の何分の一かな?」
子どもたちは自然に割合の計算を始めていた。
理科の時間は、栄養素について学習した。
「炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラル。これらのバランスが大切なんだね」
社会の時間は、給食の食材がどこから来るのかを調べた。
「お米は新潟県から」
「野菜は地元の農家から」
「魚は静岡県から」
日本地図に色を塗りながら、子どもたちは食材の流通について学んでいた。
美咲は子どもたちの変化に驚いていた。従来の授業では見られない集中力と探究心を発揮している。
ある日の職員室で、山田先生が美咲に声をかけた。
「五年三組の子どもたち、最近とても生き生きしていますね」
「そうですか?」
美咲は嬉しそうに答えた。
「廊下で会うと、給食の話ばかりしています。『今日の野菜は地元産だよ』とか『この栄養素が足りないから牛乳を飲まなきゃ』とか」
「みんな、本当に熱心に取り組んでくれています」
「でも、大変でしょう。準備が」
山田の指摘は的確だった。発芽カリキュラムの準備は、従来の授業の三倍は時間がかかる。
「確かに大変です。でも、子どもたちの反応を見ていると、やりがいを感じます」
美咲は正直に答えた。
「来年度、私たちも導入することになっています。今度、相談に乗ってもらえませんか?」
「私なんかでよろしければ」
美咲は謙遜した。
「いえいえ、実践している先生の話が一番参考になります」
第3話完
※この物語はフィクションです。登場する人物・組織名等は架空のものであり、実在の人物・企業とは関係ありません。