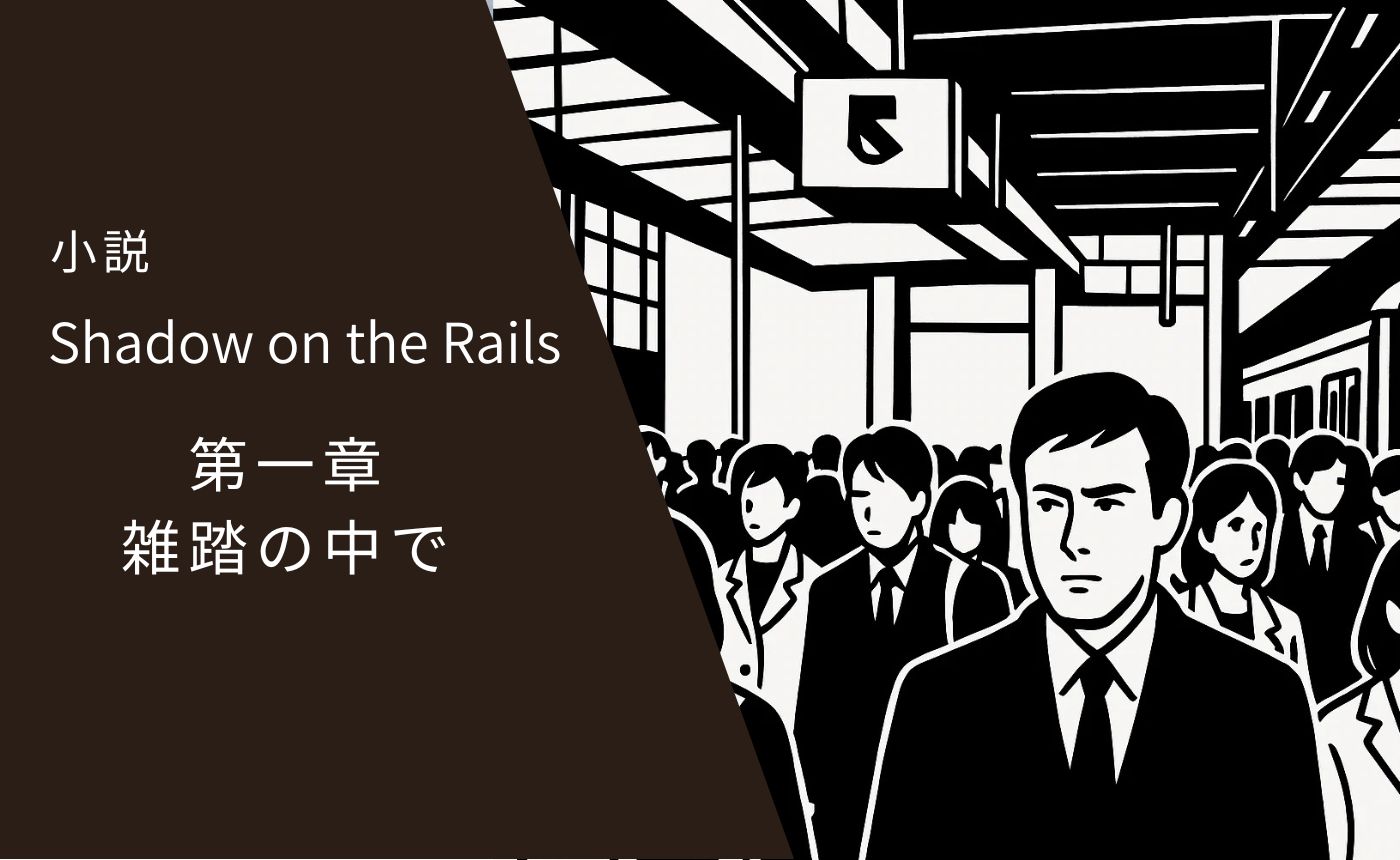※この物語はフィクションです。
午前八時半。新大阪駅のコンコースは、いつものように人波であふれていた。
スーツ姿の会社員が早足で改札へと吸い込まれていく。
スーツケースを転がす旅行客、片手にスマホ、もう片手に缶コーヒーを持つ若者、立ち止まって行き先を探す外国人観光客。
足音とアナウンスが交じり合い、天井の高い駅舎はざわめきの渦となっている。
その雑踏を、一人の男がすり抜けていた。
高田健吾、四十五歳。擦り切れたジャケットに帽子を深くかぶり、目は絶えず人の手元を追っている。
彼の手先は異様に柔らかく、自然な流れの中で財布を抜き取る。長年の習慣であり、生きるための技でもあった。
だが、今朝の彼はいつもと違っていた。
狙ったのは若いサラリーマンのポケット。だが財布ではなく、小さなUSBメモリが指先に落ちてきた瞬間、高田の目は見開かれる。
直感が告げた。これは金にならない代物ではない。もっと危険な何かだ。
その時、無線の声が駅構内に微かに響いた。
「佐伯巡査部長、スリの報告。三番ホーム付近です」
鉄道警察隊の佐伯涼介は歩みを止めた。
人混みの奥に、小さく帽子をかぶった背中が揺れているのを捉える。
嫌な予感が胸をかすめた。
――今日はただのスリ事件で終わらない。
「先輩、どうします?」
隣に立つ三浦真帆が、少し息を弾ませて問いかけた。
制服の肩口にかけた無線機が、彼女の緊張を余計に際立たせている。
入隊してまだ三か月。正義感は人一倍だが、経験は乏しい。
佐伯涼介は短く答えた。
「追うぞ。ただし、周囲に気づかれるな」
人波を切り裂くように歩き出す。新大阪駅のラッシュは、油断すればすぐに姿を見失う迷路だ。
佐伯の視線は一点に絞られていた。
帽子のつばを深く下ろした男、高田。歩き方は人混みに溶け込むように自然だが、その自然さこそが職業的な匂いを放っていた。
三浦は必死に食らいつく。
「本当にスリなんですか? ただの通行人に見えますけど」
「通行人は人を避ける。あいつは、人の後ろに吸い寄せられている」
高田は人の肩越しに何かを確かめ、すぐに視線を外す。その一瞬の動きに、佐伯は確信を深めていた。
そして――彼の指先がするりと伸び、若いサラリーマンのポケットをなぞった瞬間、光沢のある小さな物体が掌に吸い込まれた。
USBメモリ。
普通のスリなら財布を狙う。なぜこれを?
佐伯の胸に重たい疑念が落ちた。
「三浦、行くぞ」
二人は同時に歩を速める。雑踏の向こうで、高田が振り返った。目が合った一瞬、彼の瞳には妙な焦りが宿っていた。
ただの盗人の目ではない――。
高田は人混みをかき分け、東海道新幹線の改札へと向かっていた。
佐伯と三浦は距離を保ちながら追跡を続ける。
構内アナウンスが頭上に響く。
「まもなく、一番線に東京行きののぞみ二百号が到着します――」
アナウンスのリズムに合わせるように、人の流れが加速する。スーツケースの車輪が床を擦り、足音と混ざって騒音の渦をつくる。
「まずい、ホームに入るぞ」
佐伯は小さくつぶやき、無線に口を寄せた。
「対象、三番ホーム。増援を手配してくれ」
三浦の額には汗がにじむ。
「先輩、捕まえますか?」
「まだだ。証拠を確認する」
高田は改札を抜けると、列車の到着を待つ人々の間に紛れ込んだ。
背中は落ち着き払っているように見えるが、時折ポケットに触れる仕草があった。
USBメモリ。
なぜ、ただのスリがそんな物を狙う?
その時、三浦が低く声をあげた。
「先輩……後ろの黒いリュックの男、気づきました?」
佐伯が視線を動かすと、高田を遠巻きに監視するもう一人の男がいた。
浅黒い肌に無精ひげ。目は鋭く、周囲を測るように泳いでいる。ただの通勤客には見えない。
人波の中で、三人の視線が一瞬交差した。
その瞬間、高田が走り出した。
「三浦、行け!」
佐伯の号令が飛ぶ。新人の足音がホームに響き、群衆のざわめきが波のように広がった。
到着のベルが鳴り、銀色の車体がホームに滑り込んできた。
轟音とともに吹き上がる風が、並んでいた客のスーツやスカートを大きく揺らす。
一斉に動き出す人波。その瞬間を狙うように、高田は走り出した。
三浦が必死に追いすがる。
「止まれ!」
声は騒音にかき消され、周囲の誰もが振り返るだけで終わる。
黒いリュックの男も同時に動いた。人の肩を荒々しく押しのけ、高田の背後に迫る。
その鋭い視線に、佐伯は一瞬で理解した。
――これは追跡ではない、奪還だ。
高田は群衆をすり抜けながら走る。だが足取りには迷いがあった。
USBメモリを右手で握りしめ、ポケットに戻そうとした瞬間、リュックの男が肩口に飛びかかった。
もみ合いの拍子に、メモリが宙を舞い、床に小さく跳ねた。
「三浦、拾え!」
佐伯の叫びがホームに響く。
新人の身体が反射的に動き、転がるメモリへと手を伸ばす。だがその上から、リュックの男の足が無情にも踏みつけた。
目と目が合う。男の瞳は、怒りでも恐怖でもなく、どこか切迫した焦りに満ちていた。
その刹那、列車のドアが開き、乗客が雪崩れ込むように降りてきた。
人波に押され、三人の身体は引き離されていく。
佐伯は腕を伸ばし、声を張り上げた。
「離すな!あいつを――!」
しかし視界は人で埋め尽くされ、メモリの行方は群衆の足元に消えた。
人の流れに揉まれながら、三浦は必死に床を見回した。メモリは、確かに目の前にあったはずだ。
だが数百人の靴が絶え間なく行き交うホームで、小さな銀色の影はあっという間にかき消された。
「……消えた」
三浦の声は掠れていた。
リュックの男も姿を消していた。群衆の波に紛れ、列車に乗り込んだのか、それとも別の出口へ走ったのか。痕跡すら残らない。
佐伯は無線機を握りしめた。
「本部、聞こえるか。三番ホームで対象を見失った。至急、改札と出入口を封鎖してくれ。監視カメラ映像をチェック、USBメモリの行方を追う」
無線の応答が重く返る。
「了解。鉄道警察隊、本部から応援を派遣する」
その言葉に、三浦は思わず佐伯を見上げた。
「応援って、他の隊員が?」
「違う。隊全体が動くってことだ」
鉄道警察隊はふだん数人単位で駅を巡回している。
だが大規模事件の可能性があれば、各署から一斉に増援が集まる。
それはつまり、この小さなメモリが、単なるスリ事件の証拠ではないということだ。
佐伯は雑踏を見渡した。
人の波は何事もなかったかのように動き続け、ビジネスマンも観光客も、皆それぞれの日常へと歩んでいく。
だがその日常の足元に、今まさに見えない影が忍び寄っている。
「……テロの匂いがするな」
彼の独り言は、騒音に紛れて誰の耳にも届かなかった。
【次回予告】
「レールの影」第二章 消えたメモリ
スリを追う三浦巡査と、すり抜ける高田。二人の視線が交錯した時、列車のざわめきが緊張へ変わる。
登場人物
佐伯涼介(35)
鉄道警察隊の巡査部長。冷静で論理的。家族を顧みず仕事に没頭してきた。
三浦真帆(28)
新人隊員。正義感が強いが経験不足。佐伯に反発しつつ尊敬もしている。
高田健吾(45)
老練なスリ師。かつては刑務所暮らし、今は仲間を率いる。だが「なぜか高リスクなターゲットばかり狙う」違和感。
イブラヒム(32)
外国人労働者。真面目に働いていたが、祖国の紛争で家族を失い、日本で過激派の片棒を担がされる。