※この物語はフィクションです。
第一章 教室からの出発
桜賀市立南小学校の理科準備室。放課後の静けさの中、小村まさしは実験器具を片付けていた。
「先生、本当に辞めちゃうんですか?」
若手教員の声に、小村は振り返った。
「ああ。36年間、ここで子どもたちと過ごせて幸せだったよ」
「でも、どうして議員に?」
小村は窓の外を見つめた。校庭で遊ぶ子どもたち。その笑顔を守りたい。ただそれだけだった。
「教室の中だけじゃ、守れないものがあるんだ」
第二章 コロナ禍の決断
2020年春。新型コロナウイルスが桜賀市を襲った。
小村は市役所に駆け込んだ。
「桜賀病院の状況を教えてください」
「小村議員、今は立ち入り禁止で…」
「分かってます。でも市民の命がかかってるんです」
担当者は困惑した表情を浮かべた。
「発熱患者と一般患者が同じ待合室で…感染リスクが高すぎます」
小村の脳裏に、教え子たちの顔が浮かんだ。
「簡易診察室を作りましょう。すぐに」
「しかし予算が…」
「予算は後から考えます。まずは命です」
小村の目に、教師として36年間貫いてきた信念が宿っていた。
その日の夜、小村は設計図を引き始めた。プレハブでもいい。テントでもいい。とにかく患者を分離できる空間を。
第三章 猛暑との戦い
翌年の夏。記録的な猛暑が桜賀市を襲った。
「議員、大変です!」
事務所のスタッフが飛び込んできた。
「独居老人の山田さんが熱中症で倒れました」
小村は即座に立ち上がった。
「エアコンは?」
「電気代が払えないと…」
小村は拳を握りしめた。
その週末、小村は市内の公共施設を巡った。図書館、公民館、コミュニティセンター。
「ここを『涼み処』として開放できないか」
施設管理者は首を傾げた。
「勝手に開放するわけには…」
「じゃあ、正式に条例を作りましょう。猛暑日は全ての公共施設を避難所として開放する。誰でも無料で利用できるように」
第四章 子どもの笑顔のために
ある日の午後、小村は一本の電話を受けた。
「小村先生、公園の遊具が壊れていて…」
逢坂北公園。小村は現場に急行した。
ブランコの鎖が錆び、シーソーは傾いていた。
「これじゃ遊べない…」
傍らで、子どもたちが寂しそうに遊具を見つめていた。
小村は市役所に戻ると、即座に予算要求書を作成した。
「逢坂北公園だけじゃない。大海原小学校の遊具も、甲下運動公園も全部点検してください」
「全部ですか?予算が…」「子どもの安全に予算も何もあるか!」
普段は温厚な小村が珍しく声を荒げた。
「失礼しました。でも、子どもが怪我をしてからでは遅いんです」
第五章 通学路の危険
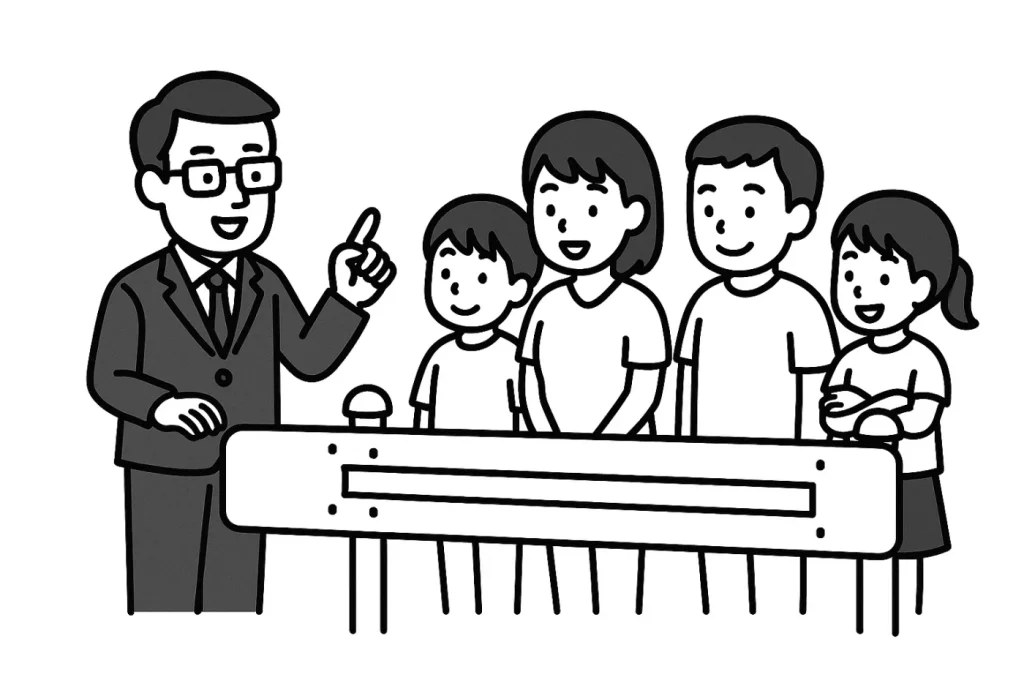
初秋のある朝。小村は通学路の見守り活動に参加していた。
「危ない!」
小学生が車道にはみ出しそうになった。小村は咄嗟に手を伸ばした。
「ここ、ガードレールないんですよね」
保護者の一人が不安そうに言った。
小村はその日、市内全ての通学路を歩いて回った。カメラを手に、危険箇所を記録していく。
翌週の議会。小村は壁一面に写真を貼り出した。
「これが現実です。子どもたちは毎日、こんな危険な道を歩いているんです」
議場が静まり返った。
「ガードパイプの設置、路面表示の整備。予算は1500万円です」
「そんな予算は…」
「では、子どもが事故に遭ってもいいとおっしゃるんですか?」
小村の声に怒りが滲んだ。
「私は36年間、子どもたちと向き合ってきました。その子たちの笑顔を守れないなら、議員なんて辞めます」
第六章 地域の声を聴く
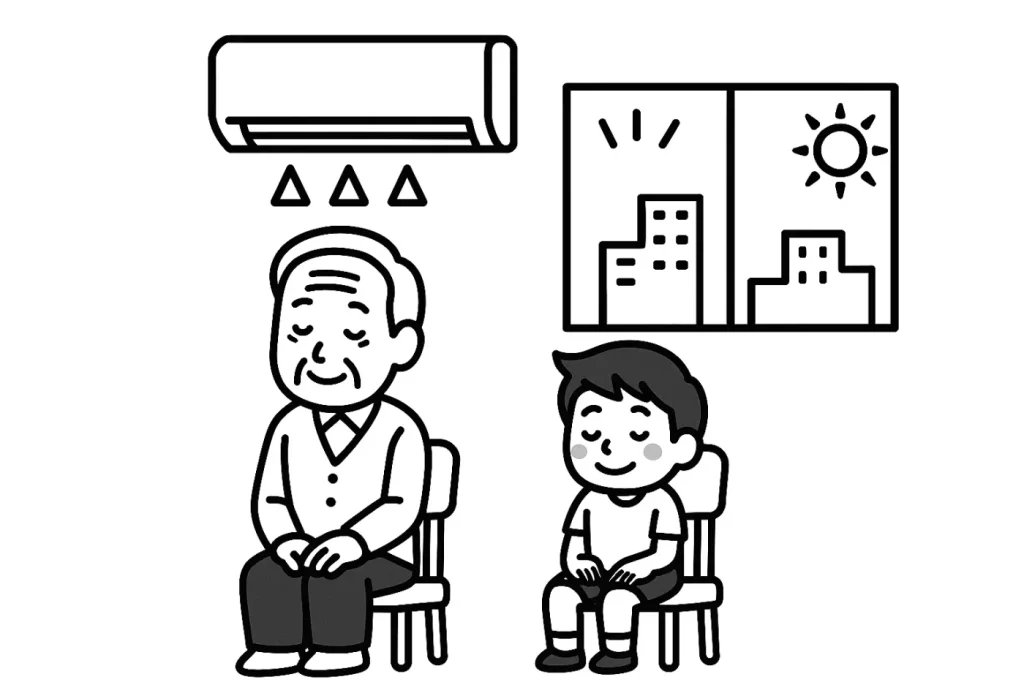
甲山コミュニティセンター。夏の暑さで、高齢者たちが集まれずにいた。
「エアコンが壊れてるんですよ」
自治会長の言葉に、小村は即座に動いた。
「予算を確保します。来月の議会で必ず」
「でも、うちみたいな小さなセンターに予算は…」
「大きいも小さいもありません。地域の集いの場が失われることの方が問題です」
小村は市役所に戻ると、甲山コミュニティセンターの空調設備更新案を提出した。
第七章 道路の安全を守る
国道1号線。雑草が生い茂り、視界を遮っていた。
「これじゃ事故が起きる」
小村は国土交通省に何度も足を運んだ。
「除草作業を前倒しでお願いできませんか」
「予算の関係で年2回が限度で…」
「では、市で予算を組みます。命には代えられません」
さらに、感応式信号の表示が見えにくいという声も届いた。
「表示を大きくしてください。高齢者にも見やすいように」
県道の凹凸路面も同様だった。小村は一つ一つ、丁寧に改修を進めていった。
第八章 防災への備え
広域農道の法面。大雨の度に土砂が崩れ落ちていた。
「いつか大きな災害になる」
地元住民の不安を受け、小村は現場を何度も視察した。
「防護壁を設置します。予算は3000万円」
議会で反対の声が上がった。
「そこまでする必要が?」
小村は立ち上がった。
「災害が起きてからでは遅いんです。予防こそが最大の防災です」
「しかし財政が…」
「ここで事故が起きたら、損害賠償はいくらになりますか?人命を失った時の損失は計算できますか?」
小村の論理は明快だった。
第九章 多様な学びの実現
ある日、一人の母親が小村の事務所を訪れた。
「うちの子、学校に行けないんです…」
「不登校ですか?」
「はい。でも、学びたい気持ちはあって…」
小村の教師としての経験が蘇った。
「分かりました。多様な学びの環境を作りましょう」
翌週、小村は教育委員会に提案書を提出した。
「フリースクールとの連携、オンライン学習の支援、適応指導教室の拡充。全ての子どもに合った学びの場を」
「予算が…」
「子どもの未来に予算を惜しむんですか?」
小村の情熱は、次第に周囲を動かしていった。
第十章 地域の未来へ
桜賀市議会。小村の任期4年目の予算委員会。
「小村議員の提案する総合政策について説明をお願いします」
小村は立ち上がった。
「私は36年間、教育現場にいました。そこで学んだことが一つあります」
議場が静まり返った。
「子どもたちは、一人一人違う。それと同じで、市民の困りごとも、地域の課題も、全て違う。だから一律の対応じゃダメなんです」
「それで?」
「だからこそ、フットワーク軽く、現場に足を運ぶ。一人一人の声を聴く。そして誠実に対応する。それが私の政治です」
小村は資料を配布した。
「障がい者・高齢者福祉の拡充、子どもの貧困対策、地域防災の強化、公共交通の充実、若者定住促進。これら全てに共通するのは、『誰一人取り残さない』という理念です」
「財源は?」
野党議員からの質問。
「まず、既存予算の見直しです。無駄を削減し、本当に必要なところに予算を回す」
「具体的には?」
「例えば、防災訓練。今は年1回、大規模にやっていますが、地域ごとに小規模で頻繁に実施する方が効果的です。コストは3割削減できます」
議場がざわめいた。
「その削減分を、防犯灯の設置や見守り体制の強化に回す。同じ予算で、より多くの市民を守れます」
「公共交通については?」
「デマンド交通の導入です。大型バスを定期運行するより、小型車両を必要に応じて運行する。コストは半分、利便性は2倍になります」
小村の説明は、データに基づいた論理的なものだった。
「さらに、若者定住促進については…」
小村は一枚の地図を広げた。
「桜賀市には豊かな自然と歴史遺産があります。これを活かした体験型観光を整備し、雇用を創出する。若者が『ここで暮らしたい』と思える魅力を作るんです」
「それは観光政策では?」
「いいえ、定住政策です。観光で人が来る→雇用が生まれる→若者が残る→子どもが増える→学校が活性化する→地域が元気になる。全て繋がっているんです」
議長が采配を振るった。
「採決に入ります」
小村は目を閉じた。36年間の教師人生。そして議員としての4年間。全てがこの瞬間に凝縮されていた。
「賛成多数により、可決!」
議場に拍手が響いた。
エピローグ 情熱と行動力と
それから1年後。
桜賀市の人口は、10年ぶりに増加に転じた。若者の移住者が前年比50%増。
小村は今日も、市民の声に耳を傾けている。
「小村先生、通学路の街灯が切れていて…」
「分かりました。すぐに確認します」
小村の携帯電話が鳴る。また新しい「困りごと」の声だった。
「はい、小村です。どこまでも誠実に!フットワーク軽く!対応させていただきます」
小村まさしの挑戦は続く。情熱と行動力で、一人一人の小さな声を大切にするために。
そして、子どもたちの笑顔があふれるまちを作るために。
(了)
著者より
この物語は、実在の政治家の実績と理念を基に構成したフィクションです。36年間の教員経験を活かし、「子どもの目線」「現場主義」「フットワークの軽さ」を貫く政治家像を「データに基づいた論理的思考」「諦めない情熱」「市民との対話」というエッセンスと融合させて描きました。

