※この物語は実際のベトナム視察レポートをもとにしていますが、ドラマチックな演出のためフィクションを含んでいます。
プロローグ ―失われたものを取り戻す旅―
「課長、もう日本に勝ち目はないんですか」
会議室で、入社3年目の田中が俺に問いかけてきた。
プレゼン資料には「日本の経済成長率」と「東南アジア諸国の成長率」のグラフが並んでいた。どう見ても、日本の線は平坦で、他のアジア諸国は右肩上がりだ。
「そんなことはない」
俺は即答した。だが、田中の目には懐疑の色が浮かんでいた。
2025年夏。大阪は北ヤードにグラングリーンができ、整然としてきた。清潔で、安全で、便利だ。だが、どこか活気が足りない。失われた35年――その言葉が、重く胸にのしかかる。
「課長」
田中が食い下がる。
「俺たち若い世代は、日本が輝いてた時代を知らないんです。バブルも、高度経済成長も。だから実感がないんですよ。本当に日本は、もう一度立ち上がれるんですか」
その言葉に、俺は答えられなかった。
「……わからない」
正直に言った。
「でも、確かめに行く」
「え?」
「ベトナムだ。かつて日本が持っていた『何か』を、もう一度この目で確かめてくる」
田中の目が見開かれた。
「俺も、連れて行ってください」
「お前、パスポート持ってるのか?」
「持ってます!」
こうして、俺たちはベトナム行きを決めた。
行き先はホーチミンでもハノイでもない。中部最大の都市、ダナンだ。
第一章 ―鼓動する街―
関西国際空港を発ち、ホーチミンを経由して、ダナン国際空港に降り立ったのは深夜だった。
タラップを降りた瞬間、生ぬるい空気が肌にまとわりついた。
「うわ、暑っ!」
田中が額の汗を拭う。
気温38度。湿度70パーセント。日本の真夏とは違う、粘りつくような熱気だ。
だが、それ以上に俺を圧倒したのは、真夜中だというのに街全体から放たれるエネルギーの奔流だった。
翌朝、ホテルを出て街を歩く。
道路を埋め尽くす無数のバイクの波。クラクションが鳴り響き、人々は笑顔で声を掛け合う。建設中の高層ビル群。空を覆うクレーンの列。
「すごい……」
田中が呟く。
「何がすごいんだ?」
「みんな、前を向いてます。目が輝いてる」
そうだ。それだ。
人々の目に、未来への確信が宿っている。自分たちの手で何かを創り出せる。そう信じている目だ。
「これが……」
俺は呟いた。
「これが、かつての日本にあったものだ」
現地ガイドのグエンさんが、流暢な日本語で話しかけてきた。
「お二人は、ハノイには行かれたことがありますか?」
「ええ、3年前に」
俺が答えると、グエンさんは微笑んだ。
「ダナンは違うでしょう?」
「……ええ、全然違う」
「ここには、”アゲアゲなムード”があるんです。日本語で言うと、そうですね……『イケイケ』?」
田中が笑った。
「死語ですよ、それ」
「でも、ぴったりな言葉です」
グエンさんが真顔で言う。
「ダナンは今、最高に『イケイケ』なんです」
第二章 ―関西圏の再来―
「ダナンを”元気だった頃の大阪”とするなら、周辺のホイアンやフエは”京都や奈良”のようなものです」
グエンさんが車を運転しながら説明する。
「活気ある都市から日帰りで古都にアクセスできる。現代の勢いと歴史・文化の重み、その両方を味わえる。これがダナンの強みなんです」
「なるほど……」
田中が窓の外を見つめながら呟く。
「大阪からUSJに行って、京都の寺巡りもできる、みたいな感じですね」
「そうです!まさにそれです!」
グエンさんが嬉しそうに頷く。
俺は黙ってフエの宮殿を見つめていた。
かつて、関西圏はこの多様性で栄えた。現代的な都市と、歴史ある古都。その両方が揃っていたから、人が集まり、文化が生まれた。
「グエンさん」
「はい?」
「ダナンは、いつからこんなに元気になったんです?」
グエンさんの表情が、一瞬だけ真剣なものに変わった。
「2010年代からです。一つの企業が、この街を変えたんです」
「一つの企業?」
「ええ。サングループです」
第三章 ―世界一への挑戦―
翌日、俺たちはバーナーヒルズへ向かった。
「まず、ロープウェイに乗ります」
グエンさんが乗り場へと案内する。
「え、いきなりロープウェイですか?」
田中が驚く。
「ええ。バーナーヒルズは山の上にあるんです。だから、まずこれに乗らないと何も見られない」
ロープウェイ乗り場に着くと、そのスケールに息を呑んだ。
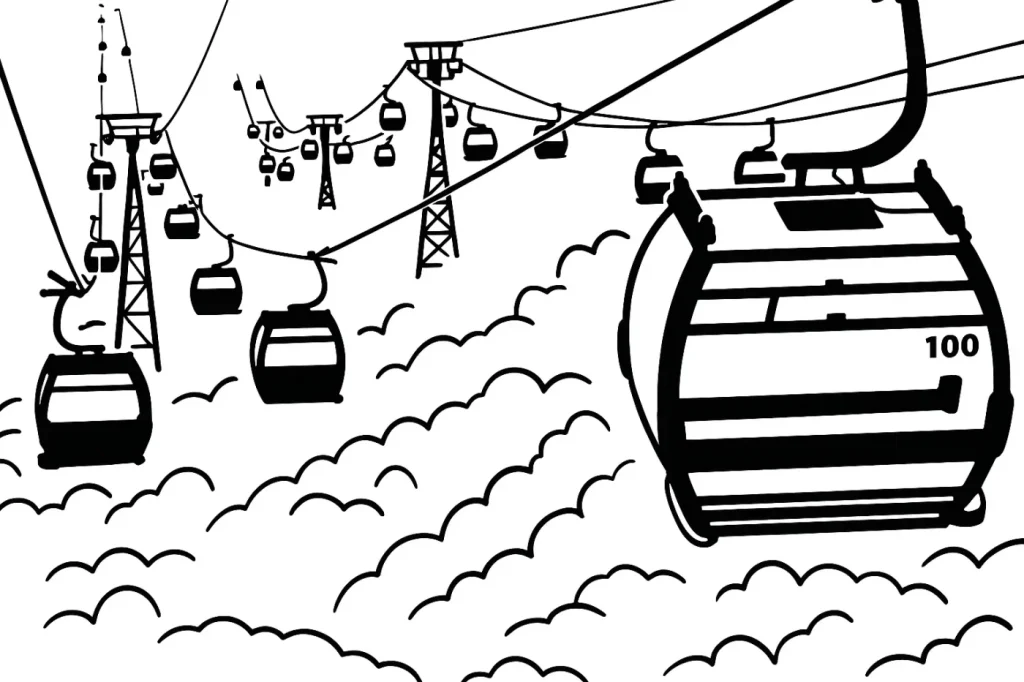
眼下には緑豊かな山々が広がり、遥か向こうには南シナ海が輝いている。そして、空に向かって伸びる、無数のロープウェイのライン。
「でかい……」
田中が呟く。
「これ、ギネス世界記録に認定されてるんです」
グエンさんが誇らしげに言う。
「世界記録?」
「ええ。距離と高低差、両方で世界一です。高低差1300メートル以上、距離5キロメートル超」
「これ、どうやって作ったんですか?」
田中が呆然と尋ねる。
「お金と、情熱と、挑戦する意志です」
グエンさんが意味深に笑う。
ゴンドラに乗り込むと、ゆっくりと上昇し始めた。
眼下に広がる景色が、どんどん小さくなっていく。街が、道路が、車が、すべてが米粒のように小さくなる。雲が、目の前を流れていく。
「うわ……すげえ」
田中が窓に張り付いている。
「これ、移動じゃないですね」
俺が呟く。
「これ自体が、観光体験だ」
「その通りです」
グエンさんが頷く。
「サングループは、自然の地形を逆手に取ったんです。山の上にテーマパークを作るという不利な条件を、最大の武器に変えた」
15分ほどのロープウェイの旅。それは、まさに空中散歩だった。
そして、山頂に到着した瞬間――
「課長!あれ!」
田中が指さす先に、それはあった。
山の上、雲の中に、巨大な手のオブジェが見えた。まるで神の手が、空に橋を架けているかのような光景だ。
「ゴールデンブリッジです」
グエンさんが説明する。
「SNSで世界中に拡散されて、ベトナム観光のシンボルになりました。みんな、この橋を撮りたくて、世界一のロープウェイに乗ってここまで来るんです」
「すげえ……」
田中が写真を撮りまくっている。
俺は窓の外を見つめながら考えていた。
これは、単なる観光施設じゃない。
挑戦の証だ。
第四章 ―完璧なオペレーション―
山頂に到着すると、そこには別世界が広がっていた。
フランス植民地時代の建築を模した街並み。花々が咲き誇る庭園。大人から子供まで楽しめるアトラクション。
「すごい人ですね」
田中が周囲を見回す。
確かに、多くの観光客で賑わっている。だが、不思議なことに混雑を感じない。
「レストランに入りましょうか」
グエンさんに促され、ヨーロッパ風のレストランに入る。
驚いたことに、ほとんど待たずに席に案内された。
「混んでるのに、なんでこんなにスムーズなんですか?」
田中が不思議そうに尋ねる。
「オペレーションが完璧なんです」
グエンさんが説明する。
「動線設計、スタッフの配置、回転率の計算。すべてが綿密に計算されてる。ユニバーサルスタジオやディズニーランドに負けないレベルです」
「でも、ここはベトナムの企業が作ったんですよね?」
「そうです。海外ブランドに頼らず、自国の文化と独創性だけでここまで作り上げたんです」
俺はフォークを置いて、グエンさんを見つめた。
「グエンさん、正直に聞きます。一体、この巨額の資金はどこから来たんですか?」
グエンさんの目が、一瞬だけ鋭くなった。
「知りたいですか?」
「ええ」
「じゃあ、今夜、特別な場所にお連れします」
第五章 ―ウクライナからの帰還―
その夜、グエンさんは俺たちを、ダナンの高級ホテルのバーに連れて行った。
窓からは、ライトアップされたドラゴンブリッジが見える。
「サングループの創業者、レ・ベト・ラムという男を知っていますか?」
グエンさんがウイスキーを傾けながら尋ねる。
「いえ、知りません」
「彼は、ベトナムの英雄です」
グエンさんの声が、低く、重くなる。
「1990年代、彼は若くしてウクライナに渡りました。当時のベトナムは貧しかった。チャンスを掴むには、外に出るしかなかったんです」
「ウクライナで何を?」
田中が身を乗り出す。
「食品製造業です。『テクノコム』という会社を立ち上げた。異国の地で、ゼロから」
グエンさんは一息ついた。
「彼が作ったインスタント麺『ミヴィナ』は、ウクライナで一大ブランドになりました。貧しいベトナム人が、ヨーロッパで成功したんです」
「すごい……」
「そして2009年」
グエンさんの目が光る。
「テクノコムは、世界的食品メーカー・ネスレに買収されました」
「買収額は?」
俺が尋ねると、グエンさんはゆっくりとグラスを置いた。
「1億3000万ドルから1億8000万ドル。日本円で、約200億円です」
田中が息を呑む。
「200億……」
「レ・ベト・ラムは、その金を故郷ベトナムに持ち帰りました。そして言ったんです」
グエンさんが、まるでその場にいたかのように語る。
「『この金で、ベトナムの未来を創る』と」
第六章 ―非上場の矜持―
「でも、200億円じゃ足りないでしょう?バーナーヒルズを作るには」
田中が疑問を口にする。
「その通りです」
グエンさんが頷く。
「サングループは、銀行融資と債券発行で資金を調達しました。でも、それができたのは、レ・ベト・ラムの実績と、ベトナム政府との強い信頼関係があったからです」
「政府との関係?」
「ええ。サングループの事業は、ベトナムの国家戦略と一致していたんです。観光立国、インフラ整備、雇用創出。政府が求めていたものを、サングループが実現した」
俺は考え込んだ。
「それって、官民一体の開発ってことですか?」
「まさに」
グエンさんが微笑む。
「日本で言えば、明治時代の財閥のようなものかもしれません」
「でも、上場はしてないんですよね?」
田中が尋ねる。
「していません。レ・ベト・ラムは、短期的な株主の利益に縛られたくないんです。彼が見ているのは、10年後、20年後のベトナムの姿です」
俺は、日本のサントリーを思い出していた。
非上場を貫きながらも、果敢に海外へ打って出る。守りではなく、攻めを選ぶ。
「サングループも、同じなんですね」
「ええ。彼らは、ベトナムの価値を信じている。後追いじゃなく、独自の道を選んだんです」
グエンさんがグラスを掲げる。
「自国文化を磨き上げ、世界に打ち出す。それがサングループの強さです」
第七章 ―影響力の拡大―
翌日、俺たちは再びバーナーヒルズを訪れた。
だが今度は、観光客としてではなく、ビジネスマンの目で見るためだ。
「課長、気づきました?」
田中が言う。
「ここで働いてるスタッフ、めちゃくちゃ多いですよね」
「ああ。何千人といるだろうな」
グエンさんが説明する。
「バーナーヒルズだけで、数千人の雇用を生んでいます。そして関連産業を含めれば、数万人規模です」
「数万人……」
「ホテル、レストラン、交通、土産物。すべてがバーナーヒルズを中心に回っている。サングループの影響力は、もはや一企業の枠を超えているんです」
俺は周囲を見回した。
笑顔で働く人々。家族連れで楽しむ観光客。みんなが、この場所に活気を与えている。
「一つの事業が、街全体を変えたんですね」
「その通りです」
グエンさんが頷く。
「でも、サングループの挑戦は、これで終わりじゃありません」
「え?」
「彼らのビジョンは、観光を超えている。空港、不動産、都市インフラ。その領域は年々拡大しているんです」
田中が目を見開く。
「それって、ベトナム経済全体に影響を与えてるってことですか?」
「ええ。サングループは、ベトナムの未来を創っている。そう言っても過言じゃありません」
第八章 ―世界一という意志―
「さあ、もう一度ロープウェイに乗りましょう」
グエンさんに促され、再びゴンドラに乗り込む。
今度は、じっくりと景色を見るためだ。
ゴンドラが上昇していく。眼下に広がる緑の山々。遥か向こうに輝く南シナ海。雲が、目の前を流れていく。
「高低差1300メートル以上、距離5キロメートル超」
田中が呟く。
「これ、どれだけの技術と資金が必要だったんだろう」
「想像を絶する額でしょうね」
俺が答える。
「でも、彼らはやり遂げた」
グエンさんが静かに言う。
「これは、単なるアトラクションじゃありません。これは、挑戦する意志の象徴なんです」
「意志……」
「ええ。世界一になる。不可能を可能にする。その意志が、このロープウェイを作り上げたんです」
俺は窓の外を見つめた。
山岳地帯をつなぐロープウェイ。観光施設であると同時に、開発の象徴でもある。
そして気づいた。
これは、ベトナムという国のメッセージなんだ。
「俺たちは、世界に挑戦する」
そう宣言しているんだ。
エピローグ ―前編の終わりに―
その夜、ホテルの屋上に立った。
眼下に広がるダナンの夜景。無数の光が、街の鼓動を伝えてくる。
「課長」
田中が隣に立つ。
「俺、わかった気がします」
「何が?」
「日本が失ったもの」
田中が夜景を見つめながら言う。
「挑戦する熱量です。失うものがないからこそ、前に進める。そういう気持ちを、俺たち日本人は忘れてしまったんじゃないですか」
俺は答えなかった。
答えられなかった。
田中の言葉が、あまりにも的を射ていたから。
「でも、まだ終わっちゃいない」
俺は呟いた。
「日本には、まだ強みがある。技術も、文化も、蓄積された知恵もある。それをどう活かすか。それが問題なんだ」
「課長……」
「明日、もう一つ大事な場所に行く」
俺は田中を見た。
「そこで、この旅の答えが見つかるかもしれない」
遠くで、ドラゴンブリッジが炎を吹き上げた。
夜空を照らす、赤い炎。
俺たちの挑戦は、まだ始まったばかりだ。
【前編・完】

