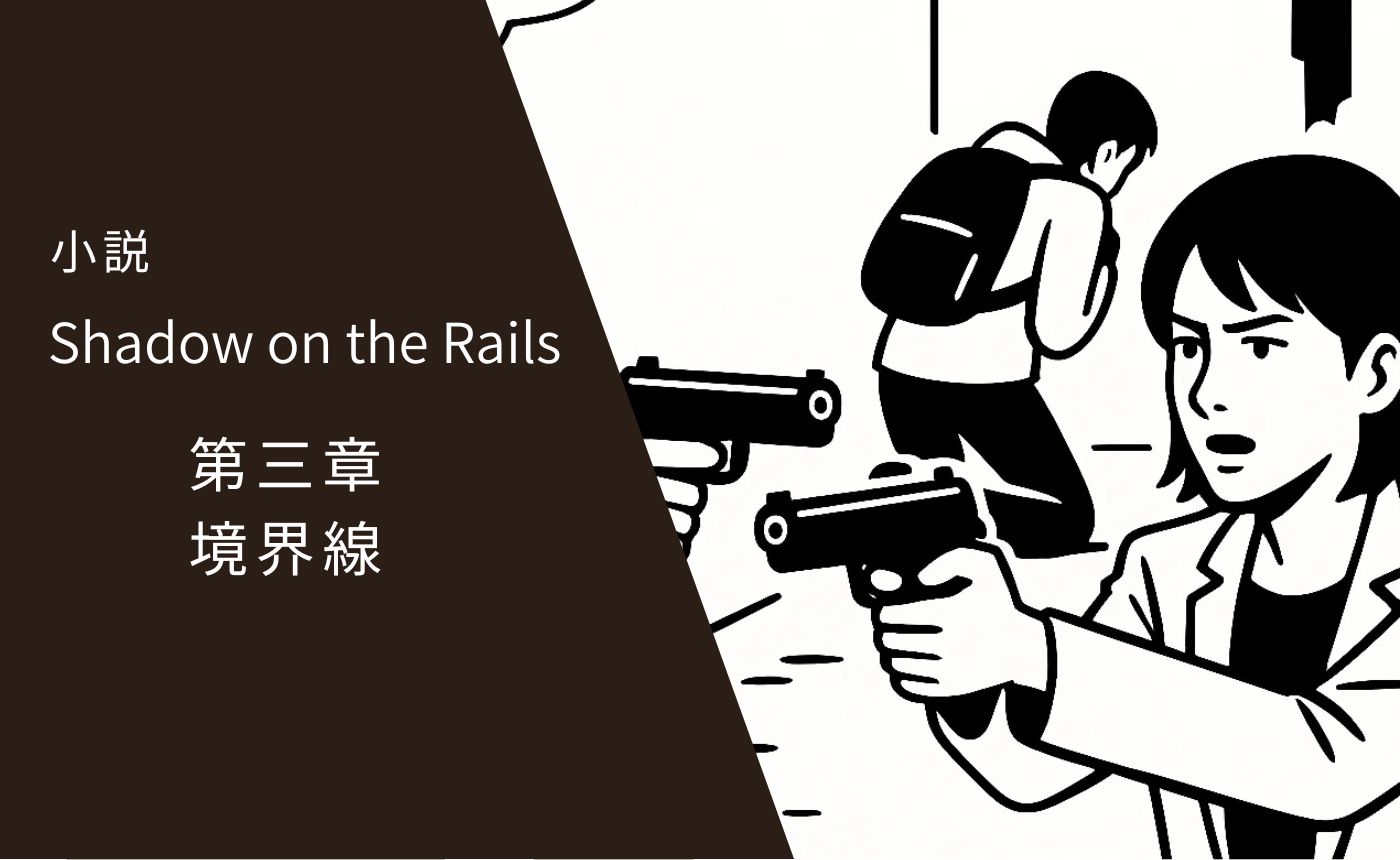※この物語はフィクションです。
「レールの影」第三章 境界線
区をまたぐ鶴橋駅で発見された不審物。境界の影に潜む何者かが、事態をさらに深刻へと導いていく。
銃声は一瞬で路地を沈黙させた。
煙の匂いが漂い、耳の奥に残響がこびりつく。
リュックの男は膝を折り、銃を落とした。腕を押さえ、呻き声をあげる。
その横で、高田は硬直し、ポケットに突っ込んだままの右手を動かせずにいた。
「武器を捨てろ!」
佐伯が鋭く命じる。三浦は震える息を吐きながら、銃口を男に向け続ける。
新人にとって初めての発砲現場――その緊張は体を痙攣させるほどだった。
しかし、安堵する暇はなかった。
無線が震えるように鳴り、管制から声が届いた。
「至急報告。鶴橋駅構内で不審物情報。爆発物の可能性あり。付近の全隊員、出動せよ」
佐伯の顔に影が落ちた。
鶴橋――大阪で最も複雑な境界線を持つ駅。天王寺区、生野区、東成区が入り乱れ、所轄署の管轄が交錯する。
対応を誤れば、情報の伝達だけで数分が失われる。数分。それは、爆発に十分な時間だ。
「……移送は応援に任せろ」
佐伯は短く言い、三浦に視線を投げた。
「俺たちは鶴橋に向かう」
高田はその言葉に反応した。
「待て……それ、メモリと関係あるんじゃねえのか?」
彼の瞳には、恐怖ではなく奇妙な決意の光が宿っていた。
「俺も行く。どうせ逃げ切れやしねえ。だったら最後まで見届けてやる」
佐伯は一瞬だけ彼を見つめ、無言で踵を返した。
境界線――区と区、人と人、正義と罪。
その曖昧な狭間へと、彼らは踏み込んでいった。
鶴橋駅に到着したとき、すでに構内は騒然としていた。
拡声器での避難誘導が響き渡り、ホームには人波が滞留している。
駅員たちは必死に通路を確保し、頭上では電光掲示板が「運転見合わせ」を繰り返し表示していた。
「不審物はどこだ」
佐伯が声を張ると、現場を押さえていた制服警官が駆け寄ってきた。
「近鉄ホームのベンチ下です。黒いリュックが放置されていました」
その言葉に三浦が息を呑んだ。
「……あの男のリュック?」
「可能性は高い」
現場に急行すると、黄色い規制テープの内側に、不気味なまでに静かな黒いリュックが置かれていた。
周囲には誰も近づけず、警備員が汗を流しながら人々を押し戻している。
佐伯は爆発物処理班の到着を待ちながら、頭の中で断片を組み合わせていた。
スリ師・高田が掠め取ったUSB。
それを奪い返そうとした外国人の男。
そして今、リュックという形で姿を現した不審物。
「先輩」
三浦が小声で囁く。
「メモリの中身……あれ、爆弾の設計図じゃないですか?」
佐伯は答えなかった。答える代わりに、無線で本部を呼び出した。
「本部、至急確認したい。押収したUSBのデータ解析、進捗は?」
数秒後、耳を刺すような返答が届いた。
「巡査部長、あのデータは……新幹線の車両構造図、それも爆破時の被害想定シミュレーションを含んでいます」
三浦の顔から血の気が引いた。
「じゃあ……やっぱり……」
「そうだ」
佐伯の声は低く、しかし確かだった。
「これはただのスリ事件じゃない。新幹線を狙った、計画的なテロだ」
構内のざわめきが遠くに霞んでいく。
人々の日常と、彼らの非日常。
その境界線の上で、鉄道警察隊の闘いは始まろうとしていた。
【次回予告】
「レールの影」第四章 迫る静寂
USBに隠された謎。沈黙の中から浮かび上がる“影の指揮者”の存在が、隊員たちを動揺させる。
登場人物
佐伯涼介(35)
鉄道警察隊の巡査部長。冷静で論理的。家族を顧みず仕事に没頭してきた。
三浦真帆(28)
新人隊員。正義感が強いが経験不足。佐伯に反発しつつ尊敬もしている。
高田健吾(45)
老練なスリ師。かつては刑務所暮らし、今は仲間を率いる。だが「なぜか高リスクなターゲットばかり狙う」違和感。
イブラヒム(32)
外国人労働者。真面目に働いていたが、祖国の紛争で家族を失い、日本で過激派の片棒を担がされる。